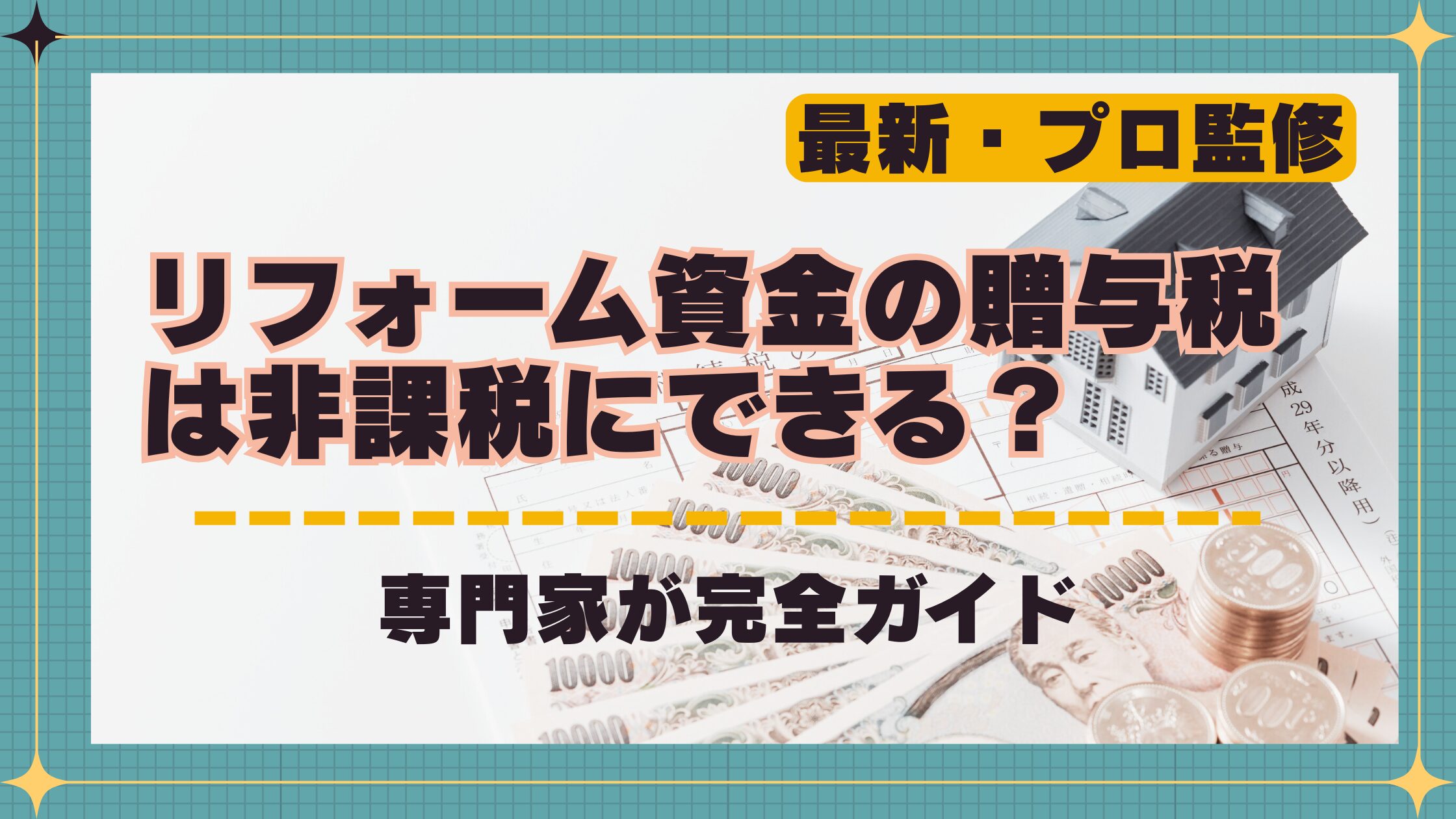「親からリフォーム資金を援助してもらいたいが、贈与税はかかるのだろうか?」
「高齢の親のために実家をバリアフリーにしたい。費用を出すと親に税金がかかると聞いたけど本当?」
マイホームのリフォームや、親が住む実家の改修を考えるとき、家族間での資金援助はごく自然な選択肢です。しかし、この「お金のやり取り」に贈与税の知識がなければ、数百万円もの想定外の税金を支払う事態になりかねません。
特に、良かれと思って子供が費用を負担した実家のリフォームが、親への高額な「みなし贈与」と判断されてしまうケースは、税務調査でも指摘されやすく、後を絶たないのが実情です。
この記事では、不動産と相続を専門とする税理士兼ファイナンシャルプランナーが、「リフォームと贈与」をテーマに、使える非課税制度を最大限に活用する方法と、危険な落とし穴を合法的に回避するための全知識を、一つの完全マニュアルとしてまとめ上げました。
この記事を最後まで読めば、あなたの状況に合わせて「贈与税をゼロにするための最適な方法」が分かり、安心してリフォーム計画を進められるようになります。計画的な資金計画で、大切な家族のためのリフォームを成功させましょう。
親子間のリフォーム資金援助|最初に知るべき贈与税の2つのパターン
リフォームに関する親子間の資金援助には、大きく分けて2つのパターンが存在します。
- 【親から子へ】
親や祖父母が、子供や孫が住む家のリフォーム資金を援助するケース。
→ 非課税制度(住宅取得等資金贈与の特例)があり、賢く使えば大きな節税が可能です。 - 【子から親へ】
子供が、親名義の実家のリフォーム費用を負担するケース。
→ 「みなし贈与」という落とし穴があり、対策しないと親に高額な贈与税がかかる危険性があります。
どちらのパターンに当てはまるかで、考えるべきことや対策が全く異なります。まずはご自身の状況がどちらに該当するかを確認し、それぞれの章をじっくりと読み進めてください。
【親から子へ】最大1,110万円が非課税!「住宅取得等資金贈与の特例」を賢く使う
まずご紹介するのは、親や祖父母からリフォーム資金の援助を受ける際に、最も効果的で活用すべき税制優遇措置「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」です。
この制度は、国が質の高い住宅を増やすことを目的に設けているもので、条件さえ満たせば非常に大きなメリットを受けられます。制度を正しく理解し、戦略的に活用することで、贈与税の負担をゼロにすることも夢ではありません。その概要と具体的な活用法を、専門家の視点から徹底的に解説します。
制度の概要|いったい、いくらまで非課税になるのか?
この特例の最大の魅力は、なんといっても非課税になる金額の大きさです。ポイントを整理しましょう。
- 対象となる贈与:父母や祖父母などの直系尊属(親やその親など)からの贈与に限られます。兄弟姉妹や配偶者の親からの贈与は対象外です。
- 適用期間:令和6年1月1日から令和8年12月31日までに行われた贈与が対象です。
非課税になる上限額は、リフォームする住宅の性能によって次の2種類に分かれます。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
| 省エネ等住宅(質の高い住宅) | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
(出典:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
さらに、この特例には素晴らしい点がもう一つあります。それは、贈与税の基本的な控除である「暦年課税の基礎控除(年間110万円)」と併用が可能なことです。
これにより、例えば性能の高い「省エ-ネ等住宅」のリフォームであれば、
1,000万円(特例の非課税枠) + 110万円(基礎控除) = 最大1,110万円
まで、贈与税を一切払うことなく資金援助を受けられるのです。
さらに大きな非課税枠も?「相続時精算課税制度」との併用
より多額の資金援助を検討している場合、「相続時精算課税制度」との併用も選択肢に入ります。この場合、特例の1,000万円に加えて、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と基礎控除110万円を組み合わせることで、最大3,610万円まで贈与税がかからずに資金を移すことも理論上は可能です。
(出典:国税庁 令和6年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る相続時精算課税選択の特例)
ただし、相続時精算課税制度は、将来の相続時に贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度であり、利用には慎重な判断が必要です。必ず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
【チェックリスト】特例の適用条件を徹底確認
この強力な特例を受けるためには、贈与を受ける人(受贈者)、住宅、リフォーム工事のそれぞれに定められた要件をすべてクリアする必要があります。一つでも満たせないと適用できないため、計画段階で必ず確認しましょう。
贈与を受ける人(受贈者)の主な要件
(出典:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税, アルファジャーナルCHANNEL)
- 贈与者の直系卑属(子や孫)であること
- 贈与をする人(親・祖父母)から見て、直接の血縁関係にある下の世代であることが必要です。子の配偶者(嫁・婿)は対象外です。
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴います。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 給与所得だけでなく、不動産所得や事業所得など、すべての所得を合計した金額です。
- 【注意】 リフォーム後の住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額1,000万円以下という、より厳しい所得要件が課されます。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにリフォーム工事を完了していること
- 原則として、工事が完了している必要があります。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住を開始していること(または、その後遅滞なく居住することが確実と見込まれること)
- 贈与資金は、自らが住むための家のリフォームに使うことが大前提です。
住宅・リフォーム工事の主な要件
(出典:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
- 日本国内にある家屋のリフォームであること
- 自身が所有し、かつ居住する家屋のリフォームであること
- 登記上の所有者が自分で、実際に自分が住んでいる家が対象です。賃貸物件のリフォームなどは対象外です。
- リフォーム後の住宅の床面積(登記簿上)が40㎡以上240㎡以下であること
- マンションの場合は、専有部分の床面積で判断します。
- リフォーム工事にかかった費用が100万円以上であること
- 消費税込みの金額で判断します。また、費用の半分以上が、自身の居住用部分の工事に充てられる必要があります。
- 工事内容が、定められた工事に該当すること
- 増改築、大規模な修繕・模様替え、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、給排水・雨水の浸入を防止する修繕などが対象となります。単なる家具や家電の購入費用は対象外です。
1,000万円の非課税枠が使える「省エネ等住宅」とは?
非課税枠が500万円から1,000万円に拡大される「省エネ等住宅」として認められるには、リフォーム後の住宅が以下のいずれかの基準に適合することを証明する必要があります。
- 省エネルギー性能:断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上
- 耐震性能:耐震等級2以上 または 免震建築物
- バリアフリー性能:高齢者等配慮対策等級3以上
(出典:国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置)
これらの基準は専門的な内容ですが、簡単に言うと「断熱性や気密性が高く、エネルギー効率が良い家」「地震に強い家」「高齢者や障害のある方が暮らしやすい家」のことです。
【ポイント】経過措置について
省エネルギー性能の基準は令和6年(2024年)から厳格化されました。しかし、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または令和6年6月30日までに建築された住宅については、改正前の基準(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)を満たせば「省エネ等住宅」とみなされる経過措置があります。
これらの性能基準を満たしていることを証明するためには、リフォームを請け負う施工会社や設計事務所に依頼し、建築士などの専門家が発行する「住宅性能証明書」や「増改築等工事証明書」といった書類を取得し、税務署に提出する必要があります。証明書の発行には数万円程度の費用がかかるのが一般的ですが、非課税枠が500万円増えるメリットを考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
手続き・必要書類・申告期限の完全ガイド
この特例を利用するためには、手続きの流れと期限を正確に把握することが何よりも重要です。
- 【最重要ポイント】
たとえ計算の結果、贈与税額がゼロになる場合でも、必ず贈与税の申告手続きが必要です。この申告を忘れると特例は一切適用されず、本来払う必要のなかった高額な贈与税と、延滞税などのペナルティが課されるリスクがあります。
(出典:アルファジャーナルCHANNEL) - 申告期間:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- 申告場所:贈与を受けた人(受贈者)の住所地を管轄する税務署
- 主な必要書類:
- 贈与税の申告書
- 戸籍謄本(贈与者との関係、つまり親子や祖父母と孫であることを証明するため)
- 源泉徴収票など(合計所得金額を証明するため)
- 登記事項証明書(不動産の所有状況や床面積を証明するため)
- 工事請負契約書の写し(リフォーム費用や工事完了日を証明するため)
- 「省エネ等住宅」の場合:上記に加えて、住宅性能証明書、増改築等工事証明書など、基準に適合することを証明する書類
- (出典:増改築.comチャンネル)
必要書類は多岐にわたるため、早めに準備を始めることが肝心です。不明な点があれば、税務署や税理士に事前に相談しましょう。
プロが教える注意点|住宅ローン控除・相続税との関係
最後に、専門家の視点から特に注意すべき2つのポイントを解説します。目先の贈与税だけでなく、将来的な税金全体を見据えた判断が重要です。
1. 住宅ローン控除との併用は可能だが、控除額が減る可能性
この特例は、リフォームローンなどを利用した場合の「住宅ローン控除」と併用することができます。しかし、注意が必要です。
住宅ローン控除の金額を計算する際、リフォームにかかった費用から、この特例で非課税となった贈与額を差し引かなければなりません。
(例) 3,000万円のリフォームで、親から1,000万円の贈与(非課税)を受け、残り2,000万円をローンで支払った場合
→ 住宅ローン控除の計算対象となる金額は、3,000万円ではなく、贈与額を差し引いた2,000万円となります。
その結果、住宅ローン控除の対象となる借入額が減少し、最終的に受けられる控除額が少なくなる可能性があります。
(出典:国税庁 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の住宅借入金等特別控除の計算)
2. 相続税の「小規模宅地等の特例」が使えなくなるリスク
ご両親の将来の相続が発生した際、同居していた実家の土地の評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」という、相続税対策の切り札とも言える非常に強力な制度があります。
しかし、この贈与税の非課税制度を利用して子供が早々に自分の家をリフォームしてしまうと、将来的に「親と同居する」という小規模宅地等の特例の適用条件を満たせなくなり、この特例が使えなくなるリスクが生じます。
目先の数百万円の贈与税を節税した結果、将来数千万円単位の相続税メリットを失うという、本末転倒な事態になりかねません。特に実家を将来相続する可能性が高い長男・長女の方は、必ず両方の影響を天秤にかけて判断すべきです。
(出典:【相続ビジネスの学校】豊田剛士)
【子から親へ】要注意!実家のリフォームで発生する「みなし贈与」の落とし穴
ここからは、もう一つの重要なパターン、「子供が親名義の実家のリフォーム費用を負担した場合」についてです。
「親孝行のために」「安全に暮らしてほしいから」といった善意の行動が、結果的に親に重い税負担を強いる「みなし贈与」という深刻な問題に発展する可能性があります。その仕組みと、具体的な回避策を徹底的に解説します。
なぜ?子供の支払いが親への贈与になる「附合」の仕組み
「子供が自分のお金でリフォームしたのに、なぜ親に贈与税がかかるの?」と疑問に思うのは当然です。この不可解な現象の背景には、民法上の「附合(ふごう)」という重要な考え方があります。
附合(ふごう)とは?
リフォームによって取り付けられたシステムキッチン、壁紙、ユニットバス、屋根材などの設備は、法的に元の建物と一体化したものと見なされ、建物の所有者(この場合は親)の所有物になるという原則です。
(出典:筋肉司法書士・佐伯ともやの法律ジム)
つまり、リフォームで設置した最新の設備を「これは自分が払ったものだから」といって、勝手に取り外して持ち出すことはできません。それらは法的に建物と一体のものとして扱われます。
この結果、税務上は「親は、子供からリフォーム代金に相当する財産的価値を無償で受け取った」と判断されます。これが「みなし贈与」の正体です。
そして重要なのは、費用を負担した子供ではなく、財産価値が増えた親に対して贈与税が課されることになる点です。
(出典:トピアちゃんねる【公式】)
税額はいくら?1,000万円のリフォームで231万円の贈与税が発生するケース
みなし贈与による税額インパクトは、決して小さなものではありません。具体的な例で見てみましょう。
- 例:子供が1,000万円で親名義の実家をリフォームした場合
贈与税の計算は以下のようになります。
(贈与額 1,000万円 – 基礎控除 110万円) × 税率40% – 控除額125万円 = 贈与税額 231万円
何も対策をしなければ、親に231万円もの高額な贈与税の納付義務が発生する可能性があるのです。
(出典:税理士法人桜税務)
※この計算は、子から親への贈与に適用される「一般贈与」の税率に基づいています。これは親から子への「特例贈与」よりも税率が高く設定されています。
【完全回避マニュアル】みなし贈与を回避する3つの合法的な対策
この恐ろしい「みなし贈与」を合法的に回避するためには、主に3つの対策が考えられます。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の状況に最も合った方法を選択することが重要です。
対策1:金銭消費貸借契約を結ぶ(単純な貸し借り)
最もシンプルな方法です。親子間で正式な「金銭消費貸借契約書」を作成し、子供が親にリフォーム資金を「貸した」という形にする方法です。親は契約書に基づいて、子供に分割または一括で返済していきます。
- メリット:
- 手続きが比較的簡単で、不動産登記などの手間や費用がかからない。
- デメリット:
- 親に返済能力と返済の事実が必要。返済実績がないと、税務署から「実質的な贈与」と見なされるリスクがある。
- 契約書は必ず作成し、返済は銀行振込などを利用して記録を残すことが不可欠。
(出典:はまだ税理士法人のちょっとお得な税金の豆知識)
対策2:リフォーム前に建物の名義を子供に移す(売買・贈与)
リフォーム工事に着手する前に、建物の所有名義自体を親から子供へ完全に移してしまう方法です。名義変更の方法としては「売買」または「贈与」が考えられます。
- メリット:
- 子供自身の所有物に対するリフォームとなるため、「みなし贈与」の問題は根本的に発生しない。
- 子供が住宅ローンを組む場合、住宅ローン控除の対象にできる。
- デメリット:
- 売買の場合: 子供が適正な価格(時価)で購入資金を用意する必要がある。安すぎる価格での売買は、差額が贈与と見なされる。
- 贈与の場合: 建物の評価額(固定資産税評価額)に対して贈与税がかかる可能性がある。ただし、築年数が古い家で評価額が低ければ、リフォーム代への課税より安く済む場合もある。
- 共通の注意点: 土地の名義は親のまま、建物だけ子の名義にすると、将来の相続時に権利関係が複雑化し、親族間トラブルの原因となる可能性がある。
(出典:不動産売買仲介チャンネル【ポラスグループ】)
対策3:建物を「共有名義」にして持分を調整する(最も現実的な方法)
専門家として最も推奨することが多く、現実的な落としどころとなるのがこの方法です。
子供が負担したリフォーム費用の価値に見合う分だけ、建物の所有権の一部(=持分)を子供に移し、親子で不動産を共有する「共有名義」にするのです。これにより、子供は自分のお金で「自分の持分」の価値を高めたことになるため、贈与にはあたりません。
【ステップと具体的な計算例】
(出典:Shimo log 司法書士 下大輔)
- 前提条件
- リフォーム前の建物評価額(固定資産税評価額):200万円
- 子供が負担するリフォーム費用:1,000万円
- ステップ1:リフォーム後の建物の全体価値を算出する
- 200万円(リフォーム前評価額) + 1,000万円(リフォーム費用) = 1,200万円
- ステップ2:それぞれの「持分割合」を計算する
- 親の持分割合: 200万円 ÷ 1,200万円 = 2/12 = 1/6
- 子供の持分割合: 1,000万円 ÷ 1,200万円 = 10/12 = 5/6
- ステップ3:計算した持分割合で「共有名義」として登記する
- 法務局で「所有権一部移転登記」の手続きを行います。このケースでは、リフォーム後に「親の持分1/6、子の持分5/6」となるように登記すれば、贈与税は発生しません。
これは法的に「代物弁済(お金の代わりにモノ(持分)で返済すること)」という扱いになり、税務上も正当な取引と認められます。
(出典:筋肉司法書士・佐伯ともやの法律ジム)
対策実行前に必ず確認すべき3つの重要ポイント
上記のいずれの対策を実行する際にも、以下の点に十分注意してください。自己判断は非常に危険です。
- 専門家への相談は必須
建物の評価額の算定、適切な持分割合の計算、契約書の作成、そして登記手続きは非常に専門的です。必ず税理士や司法書士に事前に相談し、法的に不備のない形で正確に進めるようにしてください。 - 実行のタイミングが命
特に「共有名義」にする対策や住宅ローン控除の利用を考えている場合、リフォームの請負契約を締結する前に共有名義登記を済ませておく必要があるなど、手続きの順序が極めて重要になるケースがあります。順番を間違えると、控除が使えなくなったり、贈与と認定されたりするリスクがあります。
(出典:Shimo log 司法書士 下大輔) - 親の意思能力の確認
親が認知症などで意思能力(判断能力)を失っている場合、売買契約、贈与契約、名義変更といった法律行為そのものが無効となります。成年後見制度を利用するなどの手続きが必要になり、計画が頓挫したり、非常に複雑化したりするリスクがあります。親子で元気なうちに、将来について話し合っておくことが何よりも大切です。
(出典:トピアちゃんねる【公式】)
リフォームと贈与に関するQ&A
ここでは、リフォームと贈与に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q夫婦間で、夫名義の家のリフォーム費用を妻が支払った場合はどうなりますか?
- A
親子間の場合と全く同じ考え方になります。夫への「みなし贈与」と判断され、贈与税の課税対象となる可能性があります。対策としては、妻が費用を負担した割合に応じて家の名義を夫婦の「共有名義」に変更する方法が最も有効です。
- Q「少額だから」「これくらいなら税務署にバレないだろう」は通用しますか?
- A
通用しないと考えるべきです。税務署は、相続が発生した際の相続税調査の過程で、被相続人(亡くなった親など)の過去数年間の預金移動を徹底的に調べます。その際に数百万円単位の不自然な出金があれば、その使途について必ず確認されます。また、固定資産税評価のための実地調査(航空写真の確認などを含む)の過程で、過去の大規模なリフォームが把握される可能性もあります。無申告が後から発覚した場合、本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課されます。正しく対策・申告することが、最も安全で確実な方法です。
(出典:はまだ税理士法人のちょっとお得な税金の豆知識、リフォームと贈与税の関連検索)
- Q住宅ローンを組んで親名義の実家をリフォームした場合、子供は住宅ローン控除を使えますか?
- A
原則として使えません。住宅ローン控除の厳格な適用要件の一つに「自己が所有し、かつ、自己が居住する家屋」と定められています。そのため、親名義の家のリフォームのために子供がローンを組んでも、子供は所有者ではないため控除の対象外となります。控除を受けるためには、前述の通り、リフォーム前に(共有でも構わないので)自分の名義(持分)を持っておく必要があります。
まとめ|リフォームの贈与税対策は「実行前の計画」がすべて
今回は、リフォーム資金の贈与に関する税金の知識について、2つの主要なパターンに分けて網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度まとめます。
- 【親から子への資金援助】
- 「住宅取得等資金贈与の特例」が最大1,000万円(+基礎控除110万円)まで非課税となり、非常に強力な節税策となる。
- 適用には所得や住宅、工事内容など細かい要件があるため、事前の確認が必須。
- 税額がゼロでも贈与税の申告は必ず必要。忘れると特例は適用されない。
- 【子から親への資金援助(実家リフォーム)】
- 何もしなければ「みなし贈与」と判断され、親に高額な贈与税がかかるリスクがある。
- 最も現実的で推奨される対策は、子供が費用を負担した割合に応じて「共有名義」に変更すること。
- 「貸し借り」や「名義変更」も選択肢だが、それぞれ注意点がある。
どちらのケースにおいても、最も大切なことはただ一つです。
それは「リフォーム契約やお金の移動をする前に計画を立て、専門家に相談すること」。
税金の問題は、後からでは取り返しがつかないことがほとんどです。安易な自己判断は避け、税理士や司法書士といった専門家を味方につけて、法的に安全な方法で手続きを進めることが、家族全員が心から満足できるリフォームを実現するための最短ルートです。